この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
賃貸物件でよくあるトラブルとして挙げられるのが騒音問題です。
隣室にどんな人が住んでいるかわからない以上、防音性の高いマンションを選ぶことが重要となってきます。
今回は誰でも簡単にできる賃貸マンションの防音性の見分け方について紹介していきます。
防音性の高いマンションの見分け方
防音性が高いかどうかというのは【床の厚さ】【壁(内壁)の厚さ】【窓の厚さ】の3つで決まります。
防音性能が高いマンションの見分け方自体はいくつもありますが、確実に知りたいのであれば図面を見るしかありません。
素人でも簡単に見分ける方法について紹介していきます。
マンションの構造で見分ける
一番わかりやすいのが構造別での見分け方です。
賃貸物件には大きく分けて【木造】【軽量鉄骨造】のアパートと【重量鉄骨】【鉄筋コンクリート】【鉄筋鉄骨コンクリート】のマンション合計5つに分類できます。

賃貸物件情報には必ず構造が記載されているので、これを見るだけで防音性や遮音性を一目で確認することができます。
マンションと言われているものは「重量鉄骨造」と「鉄筋コンクリート」のどちらがとなります。
重量鉄骨造は賃料的には高くないものの防音性はアパートとそれほど大きく変わらないので注意しましょう。
防音性を重視するなら鉄筋コンクリートマンションを選ぶのがおすすめ。
遮音性はL値で示されており、値が高ければ高いほど音が聞こえやすくなります。
これは日本建築学会が調査した建物の遮音性と等級の関係性です。
| 遮音等級 | 建物構造 | 音の聞こえ方 |
|---|---|---|
| L-35 | 日常生活で気になるような音はほぼ聞こえない | |
| L-40 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 | 防音性が高く外からの音も軽減される |
| L-45 | 子供の泣き声や走り回る音は多少聞こえる | |
| L-50 | 鉄筋コンクリート造 | 子供の泣き声や走り回る音は聞こえる |
| L-55 | 洗濯機や掃除機は少し聞こえるが気にならない | |
| L-60 | 重量鉄骨造 | 足音やドアの開閉音など振動を伴う音が聞こえる |
| L-65 | 軽量鉄骨造 | 多少音量は軽減されるが生活音はほぼ聞こえる |
| L-70 | 生活音はほとんど筒抜け | |
| L-75 | 木造 | 生活音は筒抜けで小さな音まで聞こえる |
遮音等級では木造が最低レベル。
アパートとくくられる構造は基本的に生活音は聞こえてしまいます。
重量鉄骨はマンションに分類されますが、軽量鉄骨アパートとほとんど同じ値となっているので防音性能にはやや不安が残ります。
とびぬけて防音性が高いのは鉄筋鉄骨コンクリート造でその次が鉄筋コンクリート造。
RC造やSRC造は床材にもコンクリートが使用されているため、多少の生活音はすべて遮音してくれる性質があります。
鉄筋コンクリート以上であれば基本的な生活音はほとんど聞こえないので快適に生活することができます。
壁の遮音性能は透過損失を評価する数値のD(もしくはDr)で表すことができます。
建築基準法施行令第22条の3によれば、界壁の遮音性能についての技術的基準値というのが定められていて、透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上が義務化されています。
| 振動数(ヘルツ) | 透過損失 |
|---|---|
| 125(低音域) | 25dB |
| 500(中音域) | 40dB |
| 2,000(高音域) | 50dB |
壁の遮音性能は透過損失を評価する数値のDで表すことができ、上記の数値の場合D-40以上が求められます。
L値とは違い、D値は高ければ高いほど防音性能も高くなります。
透過損失とは音が通り抜けたときに遮音してくれるdb(デシベル数)のことで、例えばD-40の壁に50dbの音がぶつかると、隣に聞こえる音は50-40=10dbとなります。
構造ごとに表にしたものがこちらです。
| 構造 | 壁の厚さ | D値 |
|---|---|---|
| 木造 | 130mm~145mm | 40以下 |
| 軽量鉄骨造 | 100mm~125mm | 40~ |
| 重量鉄骨造 | 125mm~150mm | 40~45程度 |
| 鉄筋コンクリート造 | 120mm~180mm | 45~60 |
あくまで目安の数値であり、壁内部の構造や壁の厚さによって遮音性は変わってきますが、鉄筋コンクリート造が最も防音性が高いです。
仮にD-50の内壁で音の種類ごとにどのように聞こえているのかを表したものがこちら。
| 音の種類 | 音の大きさ | 透過損失後 | 聞こえ方 |
|---|---|---|---|
| ドアの開閉音 | 75dB | 25dB | ほとんど聞こえない |
| 子供の走る音 | 65dB | 15dB | 聞こえない |
| 掃除機 | 70dB | 20dB | ほとんど聞こえない |
| 洗濯機の音 | 70dB | 20dB | ほとんど聞こえない |
| テレビ(中) | 60dB | 10dB | 聞こえない |
| いびき(大) | 80dB | 30dB | 小さく聞こえる |
| 大人の足音 | 45dB | 0dB | 全く聞こえない |
| 話し声 | 60dB | 10dB | 聞こえない |
| 笑い声 | 80dB | 30dB | 小さく聞こえる |
防音性の高い鉄筋コンクリートであれば突発的な騒音や重低音でない限り、日常生活レベルの音はほとんど聞こえません。
内見時に壁を叩いてみる
鉄筋コンクリートマンションでも物件によって壁の厚さは異なります。
界壁にコンクリートが使われているとは限らないので、”コンクリートを使っているかどうか”を知りたい場合は内見時に壁を叩いてみる方法が非常に有効です。
壁が薄かったり、空洞がある場合など防音性が低い部屋というのは叩くと壁全体、部屋全体に音が響きます。
一方、鉄筋コンクリート造などしっかりしている建物は叩くと「ぺチぺチ」という音が鳴ります。
最近の住宅では内壁にコンクリートが使われる場合150mm以上が多いので、コンクリートか確認できれば少なくともD-50以上(騒音トラブルになりにくい)はあるということです。
| 遮音性能 | コンクリートの厚さ |
|---|---|
| D-55 | 180mm |
| D-50 | 150mm |
| D-45 | 120mm |
| D-40 | 100mm |
音の響き方は一目瞭然なので内見時は念のため壁を叩いてみるようにすると良いでしょう。
必ずしも壁を叩いたからといって防音性が判断できるわけではありませんが、音の響き方によって厚さや素材もわかるので遮音性能の判断材料になります。
鉄筋コンクリートマンションで壁を叩いたときに反発があるようなら石膏ボードを使用しています。
石膏ボードを使用している界壁には「乾式壁」と「GL工法」があります。
【乾式壁】

コストを安く済ませているので相場よりも家賃が安かったり、高層マンション等はコンクリートを使用すると重量に耐えられないためやむを得ずにこういった境壁にしていることがあります。
壁の厚さは150mm以上あれば隣人の生活音は聞こえにくいとされているので問題ないレベルですが、多少の音が聞こえてしまうリスクはあります。
最近は石膏ボードを使った乾式壁でも技術の発達によりコンクリートが使われる壁と遜色ないレベルとなっていることもありますが、住んでみるまでわからないのが怖いところ。
コンクリートが使われている場合、一般的にはGL工法というものが主流です。

GL工法はコンクリートと石膏ボードの間に『GLボンド』で接着させる工法です。
GL工法自体は防音性が低くありませんが、コンクリートと石膏ボードの間に微妙な隙間があるため、衝撃を反響させる太鼓現象が起こりやすいのが特徴です。
壁の近くで騒いでいるときの音、肘や家具を壁にぶつけてしまったときのおとは壁全体に伝わり、隣室まで音が響きやすくなります。
GLボンドは固まるとコンクリートのような硬さとなるため、壁を複数個所叩いてみると固いところが見当たります。
内見時にしっかりと壁のチェックをすると乾式壁なのかGL工法なのか見分けることが可能です。
コンクリート打ちっぱなし、もしくはクロス直貼り物件は重量則により低音から高音まで響きにくい工法です。

Gl工法ではD-45程度の防音性ですがこの工法ではD-50以上の防音性能があります。
空洞がある場合はGL工法もしくは石膏ボードなので、確実に防音性の高い部屋に住みたいならクロス直貼り物件や打ちっぱなし物件がおすすめです。
内見時に壁を叩いて空洞があるかどうかで判断できるのも良い点です。
築年数で見分ける
築年数が古いからといって必ずしも防音性が低いとは限りませんが、新築物件や築浅物件に劣る可能性があります。
建物を建築する際には必ず建築基準法という法律に乗っ取って建設する必要がありますが、この建築基準法は定期的に改正されています。
特に1981年に建設基準法が改正されて耐震性の基準値が変わりました。
耐震性はいわば建物の強度です。強度が高ければ高いほど厚みを持たせたり、使う資材が変わるため防音性にも多少なりとも影響をもたらせます。
建築基準法によれば壁の厚さに対しての基準値は設けられていませんが、床の厚さ(スラブ)は下限値が設けられていて古い建物だと120mmで最近のものは150mm前後と言われています。
実は昔、一般的なスラブ厚は120mmでしたが、近年は150mmが標準です。また分譲マンションや優良住宅などは遮音性を確保する目的で、スラブ厚を180以上とします。
床が厚くなればなるほど当然遮音性はあがります。
足音もそうですが、話し声などは結局振動音なので床から壁に伝わることもあります。
つまり、築年数の古い建物のほうが傾向としては若干防音性が低いということになります。
2023年の現在は【築年数が42年以上】であれば旧耐震基準の建物で【築年数が42年未満】であれば新耐震基準の建物なので見分けるのは簡単です。
ラーメン構造と壁式構造
建物の構造にはさらに細かく施工方法が分かれていて【ラーメン構造】と【壁式構造】の2種類があります。

ラーメン構造は柱や梁により建物を支えているのに対して、壁式構造はその名の通り壁単位で建物を構築している平面的な構造体です。
防音性に富んでいるのが壁式構造。ラーメン構造は防音性が低いというのが特徴です。
鉄骨造や鉄筋コンクリート造はこの2つのどちらかの構造となっているのが一般的です。
RCも二つあり
— ねこねこねこ 〜 (@TQBuFftGSJzrpfZ) March 22, 2021
壁式構造とラーメン構造がある
壁式のRCが一番防音が高い
ラーメン構造は
梁が部室天井にあるのがそれ
鉄筋コンクリート造のマンションに住んでいる人がもし防音性が低いと言っているなら、ラーメン構造です。
ちなみに壁式構造はある程度の重みがあるため、5階建て以下の低層マンションにしかほとんど使われません。
見分け方としては簡単でラーメン構造は柱があるので間取りを見たときに一発でわかります。柱の部分が四角く黒く塗りつぶされていたら=ラーメン構造です。
ちょっとわかりにくいので実際の画像を見てみましょう。

出典:リノベーション前提の物件選びで気を付けたい、壁式構造とラーメン構造の違い

出典:http://www.r-lounge.jp/blogs/16
黒く塗りつぶされている部分があればラーメン構造となります。壁式の場合はこういった部分は部屋のどこにも見当たりません。
実際に検索して部屋の間取りを見てみましょう。
直接部屋を見に行かなくてもどっちの構造なのかを見分けることが出来ます。
ただ賃貸物件は壁式よりもラーメン構造の方が多いです。これに関しては必ずそうしなければならないというわけではないので参考程度にとどめておいてください。
ラーメン構造でも防音性がしっかりしている物件もあります。
ちなみに僕が現在住んでいるマンションはラーメン構造ですが、隣りの部屋の生活音等は一切聞こえません。
フローリングの材質で見分ける

防音性と聞くと壁の厚さを考えてしまいますが、床から響く音というのも関係してきます。
空間で発生した音は衝撃音が床や壁に伝わることで響き渡りますが、床の材質が良いとそれだけ吸音、遮音してくれるので壁に到達するまでに最小の波動となるわけです。
賃貸で使われる床の材質にはいくつか種類があります。
| 材質 | 遮音性 |
|---|---|
| フローリング | |
| クッションフロア | |
| フロアタイル | |
| カーペット |
カーペットを採用している賃貸物件は最近ではあまり見かけませんが、学校の音楽室なんかを想像してもらえるとわかりやすいと思います。
全面カーペットだとクッション性も高く遮音性もあるので楽器可物件などで採用されることがあります。
一般的に良く使われるのはフローリングですが、フロアタイルも非常にフローリングと見た目が似ているので正直言って素人では見分けがつきません。
確認方法としては直接触ったり、叩いてみるのがわかりやすいです。
素材が良いものを使用している場合はある程度のクッション性や弾力性があり、逆に遮音性や吸音性が低いものは硬質なのでかなり感触としては硬いです。
以前僕が住んでいた物件はクッションフロアになっていて爪で跡がつくほどのものでした。
柔らかいほど遮音性や吸音性が高くて防音性も高くなると覚えておきましょう。
窓ガラスの種類や厚さ

防音性というのは壁や床の厚さも重要ですが、特に外からくる騒音に対しては窓ガラスの種類や厚さがどの程度のものかによってかなり変わります。
窓ガラスの遮音性能は日本産業規格(JIS)が定めたT値があり、数値が高ければ高いほど遮音性能も高くなります。
| 遮音等級 | 透過損失 (500Hz) | 窓ガラスの種類 |
|---|---|---|
| T-4 | 40dB | なし |
| T-3 | 35dB | ・2重サッシ ・3m以上+5mm以上の複層ガラス |
| T-2 | 30dB | ・5mm以上の単板ガラス ・3mm以上+3mm以上の複層ガラス |
| T-1 | 25dB | ・3mm未満の単板ガラス |
賃貸物件の場合はベランダ窓に設置されている長方形の大きなガラスに注目すべきです。
| 種類 | 厚さ | 特徴 |
|---|---|---|
| フロートガラス | 2mm~8mm | 最も多く採用されているタイプの透明ガラス |
| 網入りガラス | 6.8mm・10mm | 防火ガラスと呼ばれるもので防音性が高い |
| すりガラス | 2mm~5mm | くもりガラスと呼ばれるもので団地に多い |
| ペアガラス | 6mm~12mm | 2枚のガラスを組み合わせていて防音性・断熱性が高い |
リビングガラスに採用されるのは上記の4種類です。
賃貸アパートの窓ガラスは3mm~5mm程度の厚さで、マンションの場合は網入りガラスで6.8mm以上のものを使用しているのが一般的です。
| 構造 | ガラスの厚さ | 透過損失 |
|---|---|---|
| アパート | 3mm~5mm | 25db~30dB |
| マンション | 6.8mm~ | 32db~33dB |
ガラスごとに厚さは異なりますが、木造など比較的家賃の安い物件にはフロートガラスが用いられています。
重さをほとんど感じることなく開閉することができるので、感覚的には軽いと感じますがその分遮音性は低いです。
鉄筋コンクリート造や分譲賃貸の場合は複層ガラスが用いられるケースが多く、ある程度の厚みがあるので開閉すると重さを感じます。
遮音性の高い窓ガラスというのは閉めたときの耳がキュッとなるような密閉感を得ることができるので、こういった物件は騒音対策に優れていると言えます。
路地裏など比較的交通量の少ない物件ならあまり気にする必要はありませんが、大通りや踏切近くの場合は内見時に必ず窓ガラスの厚みまでチェックするのが重要です。
防音性の高いマンションの選び方
上記で紹介した方法は防音性が高いかどうかを見分けるために知っておいて損はありませんが、例えば防音性の高いと言われている鉄筋コンクリート造でも物件によっては壁が薄いこともざらにあります。
こういった失敗をしないために防音性の高いマンションを選ぶコツについて紹介していきます。
分譲賃貸マンションを選ぶ

| 防音性 | |
|---|---|
| 家賃の安さ | |
| 壁の厚さ | 150mm~ |
| 足音 | 聞こえない |
| 話し声 | 聞こえない |
| 洗濯機を回す音 | 聞こえない |
| 壁を叩く音 | 聞こえる |
分譲賃貸は売買するために建設された質の高い建物を賃貸として提供している物件のことです。
構造上は鉄筋コンクリートマンションとなりますが、床材や窓などの素材にコストをかけているので防音性は普通の鉄筋コンクリートよりも上です。
実際に住んでみましたが、やはり床に使われている素材や窓が通常よりも厚いことで騒音で悩まされたことは一度もありません。
隣人の話し声は一度も聞こえてきたことはありませんし、生活音は皆無です。
ただし、さすがに衝撃音は吸収できないので家具やひじを壁にぶつけた音は多少聞こえます。
防音性だけで見るなら分譲賃貸が圧倒的ですが家賃が高いです。
低層マンションを選ぶ

低層マンションではラーメン構造ではなく、遮音性能に富んだ壁式構造となっていることが多いので、防音性を意識するなら高いマンションを避けるというのも手です。
理想は2階~3階建てでRC造となっている集合住宅です。
壁式構造であれば内壁もコンクリートになっていることがほとんどで、住んでから隣人の音が聞こえてしまう心配もありません。
最近ではタワーマンションよりも低層高級マンションに注目が集まっているぐらいなので、景色が二の次であれば低めの物件を選んでみましょう。
大手ハウスメーカーの中から選ぶ
防音性の高いマンションに住みたいのであれば、物件で選ぶよりも建設・施工しているハウスメーカーで選ぶのがおすすめです。
大手ハウスメーカーの中でも積水ハウスの「シャーメゾン」と大和ハウスの「D-room」は高品質クオリティの賃貸物件を提供しています。

シャーメゾンでは「シャイドシステム」、D-roomでは「サイレントハイブリットスラブ」といった防音技術があります。
| 鉄骨造 | シャーメゾン | D-room |
|---|---|---|
| 防音システム | ・シャイド50 ・シャイド55(標準仕様) | サイレントハイブリットスラブ50 |
| 採用年数 | 2011年以降 | 2012年以降 |
| 重量床衝撃音 | ・LH-55(シャイド55) ・LH-50(シャイド50) | LH-50 |
| 軽量床衝撃音 | ・LL-55(シャイド55) ・LL-45(シャイド50) | LL-40 |
| 界壁遮音等級 | D-50相当(千鳥配置) | D-50 |
築浅物件であれば防音システムを採用しているため、下手な鉄筋コンクリートマンションよりも総合的な防音性は高くておすすめです。
2つのサイトをチェックするのが面倒な場合はイエプラを使えばかなり効率的です。

| 運営会社 | 株式会社コレック |
|---|---|
| 口コミ評価(google) | ★★★★☆(4.5) |
| 対応エリア | 関東・関西 |
| 店舗数 | 2店舗 |
| 物件数 | 約10万件以上 |
| 仲介手数料 | 基本賃料1ヶ月分+税(保有不動産に依存) |
| 利用料金 | 無料 |
| 会員登録 | 必要 |
| おとり物件 | 0件 |
| 特徴 | 自宅にいながら部屋探しができる チャットでやり取りが可能 新着物件を手に入れられる 業者専用サイト「ATBB」が見られる 設定できない細かい条件を伝えられる |
イエプラはチャット完結型のネット不動産です。
イエプラを使えばチャットで「家賃10万円以内でシャーメゾンとD-roomの物件のみを教えてほしい」と言えばあとは放置で新着物件を教えてもらえます。
自分で逐一チェックせずに自分の知りたいハウスメーカーの新着物件のみを通知してくれるので効率的に部屋探しができます。
空室確認としてURLを送るだけというのも問い合わせしなくて良いのでラクです。
快適に過ごすための部屋の選び方
快適に過ごすためには防音性の高さがすべてではありません。
賃貸物件は集合住宅となるため、いくら防音性が高くても隣室や上下階が非常識だとトラブルに発展してしまいます。
家賃をなるべくあげずに快適に過ごすためにお部屋の選び方についてまとめてみました。
大通りを避ける

車の走る音は振動として付近の建物にも伝わります。
築年数が古い建物だと車が走るたびに建物が揺れるということも。
こういった物件は「駅から徒歩3分」などアピールポイントがあるため、そちらに魅力を感じてしまいますが、住んでみると後悔します。
駅から近すぎる・踏切に近い・線路に近い物件は避ける

電車の音は例えどんなに遮音性の優れている物件でも聞こえてきます。
駅近というだけで安易に物件を決めてしまうと、電車の音に悩まされることになるので注意してください。
角部屋を選ぶ

角部屋は中部屋よりも人気が高く、家賃も少し高い場合がありますが、防音性等を考えるのであれば角部屋を選ぶようにしましょう。
理由は単純で中部屋だと両隣に挟まれているので音に悩まさられる可能性が高い一方、角部屋ならそのリスクを半分に抑えることが出来ます。
例えばRC造の物件を選ぶとしても内壁に使われている素材は必ずしもコンクリートとは限りませんが、角部屋であれば外側の壁は確実にコンクリートです。
こういったことからも角部屋のほうが何かと防音性は高く、隣人トラブルにも繋がりにくいです。
ただ角部屋にもデメリットは存在するので確認しておいてください。
最上階を選ぶ

これも角部屋を選ぶ理由と同じです。
何階建てなのかは物件によって違いますが、下の階というのは上の階の足音が聞こえてきやすいです。これは鉄筋コンクリート造のマンションにも言えることです。
上の階の人が掃除機をかけ始めたり、夜飲み会でドタドタ騒いでいるとその振動は下の階に伝わります。
逆に下の階の音が上の階に漏れることはほとんどありません。
まとめ
- マンションの防音性は壁・床・窓ガラスの素材や厚さで見分ける
- 防音性の高いマンションに住みたいなら鉄筋コンクリート造以上を目安にする
- 築年数の古い物件より新しい物件のほうが防音性が高い傾向がある
- 分譲賃貸はグレードの高い素材が使われているため防音性が高い傾向がある
- 防音性の高い物件ほど家賃も高くなる
やはり防音性に優れている物件というのは誰しも憧れるのでそれなりの家賃になってしまいます。
家賃を惜しんで防音性の低い物件にするか、高い家賃を払って遮音性に富んだ物件に住むかの選択です。
もし部屋選びで失敗してしまった場合は防音グッズで対策することである程度周りからの音を緩和することもできます。
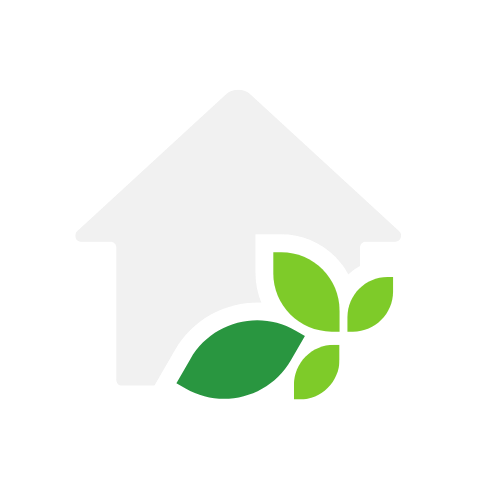 ヒトグラ
ヒトグラ